当方的2017年展覧会ベスト10
年末なので、当方が今年見に行った552の展覧会の中から、個人的に良かった展覧会を10個選んでみました。例によって順不同です。

・「泉茂 ハンサムな絵のつくりかた」展/「泉茂 PAINTINGS1971-93」展(1.27-3.26 和歌山県立近代美術館/2.25-3.26 Yoshimi Arts, the three konohana)
関西の美術館における常設展でその作品に接することが多い泉茂(1922〜95)だが、それゆえにか、一定のパースペクティヴのもとで集中して展観する機会はこれまで多くなかったわけで、美術館/ギャラリーという垣根を超えて緊密な連携のもとで行なわれた両展は関西においても貴重な機会となった。和歌山県立近美では通時的に、Yoshimi Artsとthe three konohanaでは1970年代から晩年に至るまでの絵画に焦点を当てて見せるという役割分担が行なわれていたのだが、そのことによって、泉の画業が作風の大胆な変更を繰り返していてもなお、「構造」の導入による画面の(モティーフの具象性や物語性からの)自立というモーメントにおいて一貫していたことが強い説得力を持って明らかにされていたわけで、個人的には非常に勉強になった。

・西山美なコ「wall works」展(10.24-11.12 Yoshimi Arts)
1990年代に少女趣味的あるいは少女マンガ的な意匠をあからさまに導入することによって女性性を外面的・形式的な位相に定位するような作品を多く制作したことで、前時代のいわゆる「超少女」と呼ばれた一群の女性作家たちに対する批評的な視線を内在化させた作品を多く作りだしてきた西山美なコ女史だが、近年は展示空間の壁面に直接描く作品を多く手がけているそうで。その現時点における最新版がこの展覧会だったのだが、ギャラリーの壁面にピンク色の二つの円がボヤッと浮かび上がっているという、それだけといえばそれだけ(ただし、労力は相当かかっている)の作品でありながら、ずっと見ていると視覚的にハレーションを起こすことしきり。かような形でオプ・アートを導入することで、身体に対する新たなアプローチを見せたことの意味は、身体を本質化することで90年代以降急速に反動化していったフェミニズム――西山女史の作品は、ことの最初からフェミニズム批評であり、その意味でポストフェミニズムなのである――と美術との関係を再考する上でも重要であろう。

・「福岡道雄 つくらない彫刻家」展(10.28-12.24 国立国際美術館)
大阪の現代美術界隈におけるビッグネームの一人として知られる福岡道雄(1936〜)氏の大規模な回顧展。初期作品から「つくらない彫刻家」宣言をした後の近作まで、彫刻のみならず平面なども大量に展示されていたのだが、ほとんど別人のごとき作風の変化を超えて一貫しているのは「つくる」ことを自明視することへの違和感の表明であり――既に最初期の頃に「なに一つ作らないで作家でいられること、これが僕の理想である」と表明しているのだから、相当筋金入りである――、そこから始まる迷走と中断、私的なものとの接近と乖離の軌跡をこそ見るべき展覧会であると言えるかもしれない。反芸術はなやかなりし頃に、その近傍から出てきつつ、ときに具象彫刻を作ったり、今なお豊かな謎をたたえる〈風景彫刻〉を作ったり、「何もすることがない」と大画面に細かく繰り返し書いて埋め尽くしたり……と、同年代の作家と比べてもその振れ方の凄まじさに眩暈を覚えることもないではないのだが、「反」の意味自体を問い直すこととあわせて最も「反芸術」していたのが福岡氏だったのかもしれない――そのようなことを考えさせられた。

・「抽象の力 岡﨑乾二郎の認識――現実(Concrete)展開する、抽象芸術の系譜」展(4.22-6.11 豊田市美術館)
※主催:豊田市美術館
※協力:武蔵野美術大学美術館・図書館
※企画監修:岡﨑乾二郎
※出展作家:フリードリヒ・フレーベル、マリア・モンテッソーリ、ルドルフ・シュタイナー、高松次郎、田中敦子、イミ・クネーベル、ブリンキー・パレルモ、ヨーゼフ・ボイス、ウルリヒ・リュックリーム、恩地孝四郎、熊谷守一、マルセル・デュシャン&ジャック・ヴィヨン、ジョルジュ・ブラック、エドワード・ワズワース、ドナルド・ジャッド、コンスタンティン・ブランクーシ、ペーター・ベーレンス/AEG社、ヘリット・トーマス・リートフェルト、斎藤義重、長谷川三郎、村山知義、吉原治良、ゾフィー・トイベル=アルプ、ハンス・アルプ、ジョン・ケージ、テオ・ファン・ドゥースドルフ、ピエト・モンドリアン、バート・ファン・デル・レック、瑛九、岸田劉生、坂田一男、中村彝、サルバドール・ダリ、ジョルジョ・モランディ、ル・コルビュジエ、フェルナン・レジェ、ジャン・デュビュッフェ、ルーチョ・フォンタナ、ダヴィド・ブルリューク、フランシス・ベーコン
※他、熊谷守一日記帳、ヒルマ・アフ・クリント作品のコピー、『MAVO』1-7号、『FRONT』1-10号、岸田日出刀ほか編『現代建築大観』挿画、デ・ステイル誌、『アブストラクシオン・クレアシオン』1-5号、『291』5・6号、キャサリン・ドライヤー『ブルリューク』などの各種資料
《キュビスム以降の芸術の展開の核心にあったのは唯物論である》《物質、事物は知覚をとびこえて直接、精神に働きかける。その具体性、直接性こそ抽象芸術が追究してきたものだった。アヴァンギャルド芸術の最大の武器は抽象芸術の持つ、この具体的な力であった》というステイトメントのもと、1920〜30年代をピークとして《(戦後において歪曲され忘却されていった)抽象芸術が本来、持っていたアヴァンギャルドとしての可能性を検証し直す》ことが目論まれていたのだが、岡﨑乾二郎氏による以上のような認識が、出展されていた作品が改めて並べ直されることによって眼前において雄弁に語られていたことに、個人的には驚くばかり。テキスト( http://abstract-art-as-impact.org/ )が話題になっていた様子だが、実際には「見ること」をめぐる仕掛けが随所に仕掛けられていたことにこそ、この展覧会の眼目があったと言えるかもしれない。ことに「「抽象的に」世界を認識すること」の原風景として、フレーベルやモンテッソーリたちによる知育玩具が並べられた一直線上の向こう側に田中敦子の絵画作品を望むという動線の引き方は、岡﨑氏の認識を一見即解させるものとして、実に秀逸だったわけで。ここで超展開されていることが歴史的・思想的に見てどれほどの妥当性を持っているかについてはプロたちによる検証を待ちたいが、岡﨑氏によって周到にプログラムされたzipファイルが超速でダウンロードされインストールされていくような感覚は、まさに展覧会を実地において見ることの醍醐味にあふれていたと言えるだろう。

・「アペルト06 武田雄介」展(1.27-5.6 金沢21世紀美術館(長期インスタレーションルーム))
これまでインスタレーション作品を多く作り続けてきた武田氏だが、氏の地元での金沢での個展となった今回は、〈イメージの奥行き/イメージの湿度〉というテーマ(?)のもと、様々なオブジェや映像、写真etcがざっくばらんに並べられた空間を現出させていた( https://tmblr.co/Zq0wpx2LO3SeK )。「イメージ」に対し、その質的な様相に焦点が当てられていたわけであるが、武田氏の場合、そこにとどまらず、イメージを介した諸事物の平等という方向性がこの展覧会においてハッキリと打ち出されていたわけで、それは今日において非常に慧眼であると言えるだろう。武田氏が現出させた諸事物の平等は、イメージが質的存在であることを介することで、事物を認知する主体の想像力なしに実現されることになる――氏のインスタレーションにおいて映像が特権的な位置を占めていることは、想像力による因果関係(の補完)と別種の論理が伏在している(「自由間接話法」)ことを鑑みるに、示唆的であろう。それをインスタレーションという場の実践において継続的に行なっているところに武田氏の重要性があるし、それがこの展覧会においてこれまでとは違う高レベルでなされていたことに、私たちはもっと驚くべきなのかもしれない。

・「「1968年」無数の問いの噴出の時代」展(10.11-12.10 国立歴史民俗博物館)
フランスで起こった五月革命と呼応するように日本においてその前後に同時多発的に展開された諸運動に焦点を当てた展覧会。第一部ではベ平連や成田闘争、水俣病に代表される公害問題などといった形で具現化された市民運動が、第二部では大学紛争/全共闘運動がフィーチャーされていたのだが、膨大な資料とエピソードによって語られる出来事がいちいち興味深いわけで(とりわけ「長野県には「一人ベ平連」という運動があった」とか「水俣でばら撒かれた怪文書の実物」とか、普通に瞠目しきり)、それらを「無数の問いの噴出の時代」という形でパッケージングしたところに、主催者側の慧眼が光る――それは必然的に「無数の問い」を「唯一の回答」に回収する戦後民主主義への批判を(主張が表面的には一致していたにしても)潜在的に含みこんでいるからである。近年の動向として、日本における市民意識の頂点として1960年の安保闘争を置くか1968年前後の諸動向を置くかで大きく二分されてきているのだが、後者のアクチュアリティを現在において改めて見せたところに、この展覧会の特筆大書すべき美質が存在する。

・柳瀬安里「光のない。」展(3.7-12 KUNST ARZT)
今年も近現代史や社会的な諸問題を直接的に主題とした作品ないしプロジェクト――それらは往々にして「Socially Engaged Art」(SEA)と呼ばれている――を目にする機会がそれなりにあり、特に「戦後日本」という時空間を俎上に乗せることで近現代史を主題とした展覧会にエッジの効いたものがいくつかあったのは個人的に大きな収穫だったのだが(笹川治子「リコレクション―ベニヤの魚」展(8.25〜9.17 Yoshimi Arts)、井上裕加里「堆積する空気」展(8.1〜13 Gallery PARC)など)、その中でもダントツにヤバかったのがこれ。米軍のヘリパッド建設問題で反対派と機動隊が真っ向から衝突している沖縄県東村の高江地区に赴き、建設現場の近辺をエルフリーデ・イェリネクの戯曲『光のない。』を朗読しながらめぐるという映像作品なのだが、同作において主題化されている(と考えられる)「私(たち)とは誰か」、あるいは「「私(たち)/彼(ら)」を分かつものは何か」という問いを、「私(たち)/彼(ら)」をめぐる争いが最も激烈な形で展開されている高江地区において再演するというフレームワークは、畢竟「私(たち)/彼(ら)」という線引きを固定的なものとさせてきた戦後日本/戦後民主主義に対する見直しを見る側に迫ることになるし、『光のない。』自体がもともと東日本大震災に触発されて、「デモクラシーの黄昏」というお題へのレスポンスとして書かれたという事実を外挿することで、沖縄における事態が端的に戦後民主主義の黄昏であることをも含むことになるだろう。それは「68年革命」とその日本における徴候としての「戦後民主主義批判」において既に告知され、露呈していたのではなかったか。SEA(や、それを持ち上げる社会学者)に欠けているのは、問題をそれとして取り上げるときのフレームワークに対する、かような批判なのである。
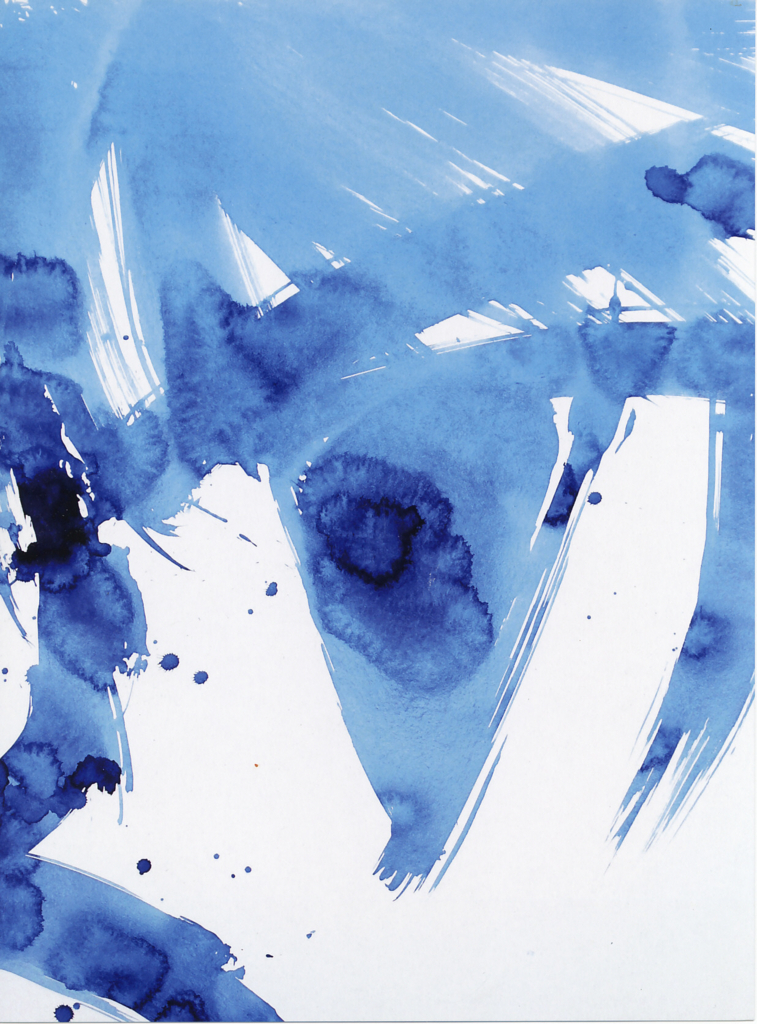
・清方「オーシャン」展(5.19-6.4 波さがしてっから)
清方(1990〜)氏の数年ぶりの個展となったこの展覧会の、京都というローカルな場におけるトランスローカルな史的過程という観点から見た位置づけについては会期中に書いたことがあるので( https://mastodon.xyz/@wakarimi075/3625002 )、詳しくはそちらを参照されたいが、そういった位相とも交差しつつ描かれていったのが「夏」や「海」を彷彿とさせる絵画であったことの意味もまた大きなものがあったのではないだろうか。ローカル/トランスローカルな位相におけるプロセスを経ることで、氏の描く「夏」や「海」が、かつて松井みどり女史がキューレーターとなって開催された「夏への扉:マイクロポップの時代」展(2007 水戸芸術館)への正当的な応答として機能していること、その意味で新しいSummer of Loveとなっていることが、今後の絵画において清方氏や、協力者としてクレジットされているKim Okko氏を正当に再評価する上で(この展覧会は、その序章である)真っ先に考察されるべきことなのかもしれない。
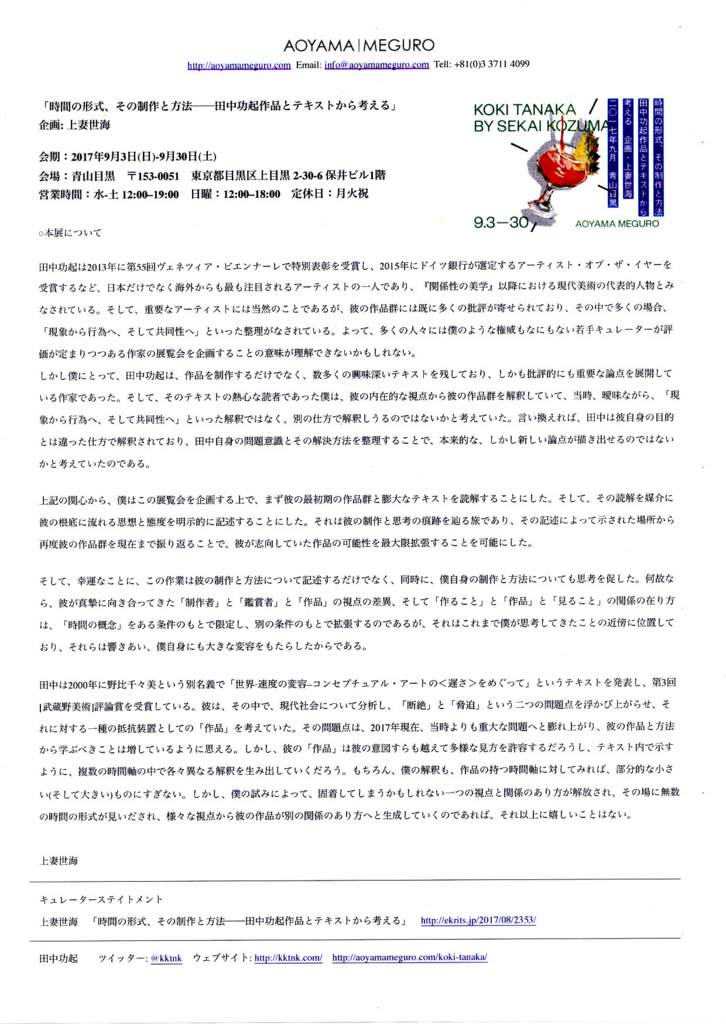
・「時間の形式、その制作と方法――田中功起作品とテキストから考える」展(9.3-30 青山|目黒)
田中功起氏の作品に対する長大な論( http://ekrits.jp/2017/08/2353/ )を提示し、それを発表/検証する場として展覧会という方法を用いるという上妻世海(1989〜)氏の企画力に、素直にすごいなぁと思ってしまうことしきりだった展覧会。大阪ではこういう企画はまぁ成立しない← それはともかくとして、田中氏が2000年に野比千々美名義で書いた論文「世界―速度の変容 ――コンセプチュアル・アートの「遅さ」をめぐって――」を出発点に、氏の名声を定着させた映像作品(同じ行為を複数の人間にさせる、というような)以前の、同じ状況が無限に繰り返されたり引き伸ばされたりしているような映像作品を多く選択し、それらを近年の(ポスト)関係性の美学の作家の一人としての田中氏に接続させるところに、上妻氏の賭金が存在していたのだが、そのような形で批評を展覧会に落とし込むのは、個人的には非常に新鮮な鑑賞体験だった。田中氏の制作活動を《バラバラになった僕たちを繋ぐ装置として、制作を考えていたのだ》という形で再提示(リバースエンジニアリング)するのは、今日において非常に重要な論点であろう。

・「不純物と免疫」展(10.14-11.26 トーキョーアーツアンドスペース本郷)
※出展作家:大和田俊、佐々木健、谷中佑輔、仲本拡史、百頭たけし、迎英里子
※キュレーター:長谷川新
※協賛:アイ・オー・データ機器、ERIKA MATSUSHIMA、gigei10
※協力:青山|目黒、スタジオ常世、This and That、tochka|特火点、PARADISE AIR
「批評」を提示/検証する場として展覧会という方法を用いつつ、こちらはもっと作品寄りというか、作品に語らせることに主眼を置いていた展覧会。ロベルト・エスポジトやジョルジュ・カンギレムの議論から着想されたと思しき自己免疫性の議論から出発しつつ、一定の度合いを越えると自己破壊を始めてしまう免疫システムからの連想で政治思想や社会思想を再考するという近年の動向に目配せしながら「不純物」としての作家と作品を提示するというフレームワーク――長谷川氏のテクスト「不純物と免疫」における《自分たち自身がまず「不純物」であり、また別の不純物たちとの折衝によってその都度規定されている存在として引き受ける地点が存在している》という一節は、それを端的に言い表している――は、今日における自己免疫性の全面化という状況に対する介入として、最低限踏まえていなければならないことであろう。なおこの展覧会は来年沖縄に巡回するという。自己免疫性の議論が最も試されている場所とも言える沖縄においてこの展覧会がどのように見られるか、興味深い。