当方的2019年展覧会ベスト10
年末なので、当方が今年見に行った515の展覧会の中から、個人的に良かった展覧会を10選んでみました。例によって順不同です。
・「Oh!マツリ☆ゴト 昭和・平成のヒーロー&ピーポー」展(1.12〜3.17、兵庫県立美術館)


※出展作家:小川治平、今和次郎、岡本唐貴、安井仲治、阿部合成、鶴岡政男、内田厳、桂ゆき、上野誠、靉嘔、河原温、石井茂雄、中西夏之、長野重一、東松照明、佐々木正芳、柳幸典、会田誠、小林秀恒、堀野正雄、川上澄生、北川民次、ハイレッド・センター、平田実、中村宏、秋山祐徳太子、郭徳俊、北蓮蔵、小野佐世男、松本竣介、木村伊兵衛、桂川寛、小林ひろし、山下菊二、村井督侍、立石紘一、松本俊夫(音楽:秋山邦晴)、福沢一郎、白川昌生、Chim↑Pom、田河水泡、瀬尾光世、榎本千花俊、藤田嗣治、鶴田吾郎、川端龍子、宮本三郎、谷内六郎、ハナヤ勘兵衛、赤瀬川原平、太田三郎、石元泰博、しりあがり寿、他各種資料
※委嘱新作出展作家:柳瀬安里、会田誠、石川竜一、しりあがり寿
一見するとおふざけが過ぎるように見えるタイトルとは裏腹に、「前衛」と「大衆」との関係を「ヒーロー」と「ピーポー(people)」の関係と読み替えた上で、その双方のあり方、ありようの軌跡を美術作品にとどまらずマンガや特撮、アニメといったサブカルチャー全般、果ては今和次郎による「考現学」に至るまで幅広く渉猟してパッケージングして見せるという豪腕&辣腕ぶりが印象的だった展覧会。昭和初期から昭和40年代あたりまでの時期が集中的に俎上に乗せられていたのだが、その中において「ヒーロー」と「ピーポー」とのカップリングの一体性が自明視されていた時代からスターリン批判、60年安保を経て「(20世紀唯一の世界革命としての)68年革命」&70年安保において決定的に分離してしまう──アラン・バディウが毛沢東の文革期における講話の一節「一は自ら二に割れる」を引用しつつ述べるのは、端的にこのような事態である──という文化/政治のプロセスが改めて浮かび上がってくるように構成されていたのがポイント高。この展覧会のために委嘱された新作も、同展においてほぼ空白とされている1970年代以降の「ピーポー」を問う作品が揃っていて(特に炎上案件になりそうになった会田誠氏のは、きわめてクリティカルであった)、そこも要注目。
・「HUB IBARAKI ART PROJECT 2018-2019」(3.30〜9.29及び5.26、茨木市内各所)

※選定作家:冬木遼太郎
※チーフディレクター:山中俊広
詳細はこちら→ https://privatter.net/p/4640353
──「「アート/作品」が茨木のまちに作用し続ける6か月間」というキャッチフレーズのもと、一日だけのパフォーマンス作品と半年間にわたる公開・非公開のトークやワークショップetcを同時並行的に進めていくという形でなされていたが、やはりメインとなる作品《突然の風景》が非常に良かったわけで。グラウンドに16台の車を配置し、クラクション音によって坂本九の「上を向いて歩こう」を演奏(演奏?)するというものだったが、かかる作品のありようと実際の状況が、観客に何かを訴え鑑賞以上の行為に向けて促していくという社会参加型アート(socially engaged art)に対する批評/批判としてあり、そのような作品を茨木市の中心部においてやってのけたことの意義はいくら強調してもし過ぎではあるまい。「上を向いて歩こう」は高度経済成長期の日本の市民社会のアンセムであったと同時にアメリカのヒットチャートで一位になったことがあるという事実によって、戦後民主主義が不可避的に帯びる一国主義を揺さぶる楽曲としてもあるという二重性を持っている。そんな来歴を持った楽曲を選曲したことは、社会参加型アートの現在-近未来に対する抵抗として上手いし、きわめてクリティカルであろう。アーティストの社会や政治運動への参加を称揚する社会学者や活動家が端的に欠いているのは、このような批評的目線なのである。
・「大阪中之島美術館開館プレイベント2019 新収蔵品:サラ・モリス《サクラ》」(9.21〜10.6アートエリアB1)

2022年に開館する予定の大阪中之島美術館が今年購入したサラ・モリス《サクラ》のお披露目会といった趣の展覧会。サラ・モリス《サクラ》は大阪市内(とその周辺(万博公園、堺市内、京大iPS細胞研究所、サントリー山崎蒸溜所など))を撮影した諸断片をつなぎ合わせた50分ほどの映像作品だが、単に大阪の名所を映しただけの作品ではなく、大阪が近世以降20世紀半ばまで日本資本主義の中心的存在だったことに注目しつつ、映像の中で描かれた(車やクレーン、ベルトコンベアなどの)運動が資本主義が要請する〈資本〉の運動とシンクロするように構成されることで──「スペクタクルとは、イメージと化すまでに集中の度を増した資本である」というギー・ドゥボールのアフォリズムが思い出される──大阪という場所自体の本質が〈資本〉の運動にあることを遂行的に描くという離れ業をサラっとやってのけていて、瞠目しきり。これはええ買い物しはりましたわ。サラ・モリス(1967〜)は世界各地の都市を俎上に乗せた映像作品シリーズを長く手がけているそうだが、都市を成り立たせる下部構造自体の運動に着目しているところに、コンセプチュアルアートの担い手としての確かさがある。あと音楽がリアム・ギリックだったことに驚かされた。
・エリック・ゼッタクイスト「オブジェクト・ポートレイト」展(2018.12.8〜2019.2.11、大阪市立東洋陶磁美術館)


ニューヨークを拠点にしている写真家エリック・ゼッタクイスト(1962〜)が同美術館の名品を撮影し、その写真を被写体となった陶磁器と並べて展示するという展覧会だったが、ストレートに撮影するのではなく、被写体を白黒で部分的なフォルムあるいはそれすら消去されたミニマルな何かに置き換えてしまうように撮影されており、その繊細にして剛腕っぷりが、鑑賞者が往々にして自明の前提にする「いい仕事」や「気色」といった骨董趣味=なんでも鑑定団的な目線を唯物的な目線にヴァージョンアップさせていて、きわめて痛快であった。ゼッタクイストは杉本博司氏のもとで写真と古美術の薫陶を受けて現在の作風を確立させたそうだが、それもさもありなん。一昨年〜昨年の「唐代胡人俑+今を生きる人間像」展に続き、大阪市立東洋陶磁美術館が展覧会という形でコレクションと現代美術とをコラボさせたり、あるいはコレクションの現代性を問いかけたりするときの外さなさが光る好展覧会となったのだった。
・「タイムライン 時間に触れるいくつかの方法」展(4.24〜6.23、京都大学総合博物館)

※出展作家:井田照一、大野綾子、加藤巧、𡈽方大、ミルク倉庫+ココナッツ
詳細はこちら→ https://privatter.net/p/4530947
SNSのUIという形で私たちの生活に定着したと言える「タイムライン」がもたらした「時間」観の変容から〈もの〉をめぐる技芸としての美術を改めて主題化するという、きわめて野心的な展覧会。「タイムライン」という体制は呟きや記事、画像、動画などなどがそれ自体相互の脈絡をほぼ持たないまま時間の流れに沿って配置され、それを追尾していくという一連の行為を可能にするのだが、それは単一の時間軸という概念を一方で強化しつつ、しかし「違ったタイムライン上にいる自分以外の誰か」を思い出させることによって複数の時間に開かせる契機にもなりうる。その意味でこれまで文学的・レトリカルに考えられてきた「複数の時間」「複数の歴史」がリテラルに実現している/しつつある状況にあるわけで、そのような状況をいかなる形で可視化しつつ応接するかが(裏)主題になっていたと言えるだろう。個人的には身近な例などをうまくアレンジして私たちが「時間をスキップする」「未来を先取りする」といったSFめいた状況に普段の生活の中で意識することなく接していることを説明的に示して見せたミルク倉庫+ココナッツや、自作のペインティングを科学的な分析にかけ、その結果できた画像(画像?)も絵画として展示した加藤巧氏の作品がクリティカルだった。
・堂島リバービエンナーレ2019(7.27〜8.18、堂島リバーフォーラム)

※出展作家:ゲルハルト・リヒター、トーマス・ルフ、フィオナ・タン、ダレン・アーモンド、佐藤允、空音央/アルバート・トーレン、ジャン=リュック・ゴダール
※アーティスティックディレクター:飯田高誉
一人のディレクターによるグループ展という形式では4年ぶりの開催となった今回は「シネマの芸術学─東方に導かれて─ ジャン=リュック・ゴダール『イメージの本』に誘われて」というタイトルで(二度目の登板となった)飯田高誉氏がディレクションを行なっていたが、出展作の中でもリヒター《アトラス》に超瞠目。1960年代から最近に至るまでの自身の作品のエスキースやメモランダム、イメージソースのスクラップをまとめたこの作品、今回ドイツから800点以上が一挙に出展されており、いやこれナンボかかってん!? と呆然とすることしきり。「資本主義リアリズム」から《抽象絵画》シリーズ、近年のストライプの作品に至るまでのリヒターの移り変わりはもちろん、ドイツ現代史の暗部──ホロコーストはもちろん、ドイツ赤軍の幹部が獄中で謎の死を遂げたバーダー&マインホーフ事件も特権的なものとなっている──をも主題としていることで、単なるリヒターのネタ帳にとどまらない広がりをともなっているこの作品を今の日本で見ることの意義は、きわめて大きい。《アトラス》は正義。他の出展作家も「イメージ」が自立/自律して久しい現在に対する局地的な陣地戦として自作を展開していっており、きわめて緊張感の高い展覧会であった。
・TRANS- ART PROJECT KOBE 2019(9.14〜11.10神戸市内各所)

※出展作家:グレゴール・シュナイダー、やなぎみわ
詳細はこちら→ https://tmblr.co/ZAlCrV2lx_-Is
出展作家を二人に絞ったことが開催前から話題となっていたが、やなぎみわ女史は自身の演出のもとここ数年各地で展開している舞台版『日輪の翼』の巡回公演だったため(未見)、実質的にはグレゴール・シュナイダー(1967〜)の個展状態だった。そのシュナイダーの作品《美術館の終焉─12の道行き》は神戸市内各所に12の自作を設置し、観客はそれらを巡回していくのだが、その自作がいちいち不穏だったわけで。例えば新開地駅の地下通路に設置された第4留では、扉を開けると真っ暗な部屋があり、さらに扉を開けると浴室を模したスペースがある。以下、暗室→浴室というパターンが十数回繰り返されるというもので、方向感覚や平衡感覚が失われていく恐怖感があった。他にも(元)公共の施設から果ては(実際に居住者がいる)民家まで使って、都市の片隅に開いた穴のように作品を制作していっており、その大規模さには驚かされるところ。
・ジャコメッティと I&II(I: 5.25〜8.4、II: 8.27〜12.8、 国立国際美術館)


※「ジャコメッティと I」出展作家:アルベルト・ジャコメッティ、ポール・セザンヌ、パブロ・ピカソ、佐伯祐三、ジョルジョ・モランディ、ヴァシリー・カンディンスキー、ジュール・パスキン、藤田嗣治、カレル・アペル、オシップ・ザッキン、舟越保武、ジャコモ・マンズー、佐藤忠良、荒川修作、ジャン・デュビュッフェ、ヴォルス、ジャン・フォートリエ、アンリ・ミショー、堂本尚郎、ピエール・アレシンスキー、上前智祐、白髪一雄、今井俊満、嶋本昭三、正延正俊、山崎つる子、元永定正、吉原治良、安斎重男、尾藤豊、阿部展也、石井茂雄、泉茂、靉嘔、三木富雄、鶴岡政男、菅井汲、田淵安一、他矢内原伊作収蔵の各種資料
※「ジャコメッティと II」出展作家:アルベルト・ジャコメッティ、今村源、トニー・クラッグ、リュック・タイマンス、シュテファン・バルケンホール、ゲオルク・バゼリッツ、マルレーネ・デュマス、加藤泉、ジュリアン・オピー、南川史門、森淳一、鈴木友昌、西尾康之、棚田康司、トーマス・ルフ、ロレッタ・ラックス、ボリス・ミハイロフ、石内都、北野謙、ミケランジェロ・ピストレット、内藤礼、高松次郎、オノデラユキ、工藤哲巳、荒川修作、草間彌生、米田知子、アラヤー・ラートチャムルーンスック、シェリー・レヴィーン、テリーサ・ハバード/アレクサンダー・ビルヒラー、饒加恩、加藤翼、塩見允枝子、池水慶一、小沢剛、ヒーメン・チョン
国立国際美術館がアルベルト・ジャコメッティ(1901〜66)の彫刻作品《ヤナイハラ I》を新収蔵品としたことを記念してたっぷりと会期を取って開催されたこの展覧会。「I」ではジャコメッティ以前から同時代における美術動向から、「II」ではジャコメッティ以後における現代美術から国立国際美術館が所蔵している作品を展示するという形を取っていたが、そうすることによってモダンアートとコンテンポラリーアートの双方から、双方に越境しうる存在としてジャコメッティと《ヤナイハラ I》の真価を問い直すことが遂行的に行なわれていたことになるわけで、これは趣向としてなかなか面白かった。個人的にはテリーサ・ハバード/アレクサンダー・ビルヒラーの映像作品──パリに渡って美術を学びながらジャコメッティの愛人となるも挫折してアメリカに戻った女性の話をその息子が回顧する、という──に(「トラベラー」展以来)再見できたのが収穫。
・岡山芸術交流2019(9.27〜11.24、岡山市内各所)

※出展作家:タレク・アトウィ、マシュー・バーニー、エティエンヌ・シャンボー、ポール・チャン、イアン・チェン、メリッサ・ダビン&アーロン・ダヴィッドソン、ジョン・ジェラード、ファビアン・ジロー&ラファエル・シボーニ、グラスビード、エリザベス・エナフ、エヴァ・ロエスト、フェルナンド・オルテガ、シーン・ラスペット、リリー・レイノー=ドゥヴァール、パメラ・ローゼンクランツ、ティノ・セーガル、ミカ・タジマ、ピエール・ユイグ
2016年にリアム・ギリックをディレクターに迎えて開催されたが、それから三年経った今回はピエール・ユイグをディレクターに「IF THE SNAKE もし蛇が」という(いささか謎めいた)テーマでの開催に。《展覧会「もし蛇が」は、独立した一つの生命体である》(図録より)──ユイグは今回ディレクションするにあたって、以上のような形で展覧会を構成するよう作家や作品を選んだそうで、実際、ユイグ自身のも含めて、生命や情報科学技術、およびそれらが起動するアルゴリズムによってなされる異種交配が産み出すシステムを俎上に乗せたであろうことを思弁的に予感させる作品が多く、「一つの生命体」とは言い得て妙である。結果として自然と「テクノロジー」と人間という三項関係から出発することでエコロジーをめぐる「マイナー哲学」(ドゥルーズ+ガタリ)を駆動させていたわけで、美術をそのような技芸へとバージョンアップさせようという不穏な試みをここまで大規模に行なったことは、非常に意義深い。《「既知」に束縛された合意形成に依拠する現実から旅立つためには、フィクションのもつ不確かな要素が必要だ》(図録より)。
・高柳恵里「性能、その他」展(1.26〜2.16、SAI Gallery)

日用品とそれを用いた行為自体を作品として提示することで、1990年代以降の日本現代美術界において特異な位置を占めてきている高柳恵里女史。SAI Galleryで数年ぶりとなる今回の個展では、何種類かの枝切りばさみと、それが切ったであろう枝が出展されていた。「このはさみはあのはさみの数倍切れ味がいい」というようなキャッチコピーはありふれているが、「切れ味」という数値化できる基準が全く想定できない観念に対して「数倍」という比較が果たして意味があるのかというところから出発しているそうで、そこから展開(?)された作品は、ものとは異なる観念・概念を、より正確には「このはさみはあのはさみの数倍切れ味がいい」と言うこと自体が遂行的に基準らしきものを作ってしまうという意味において実態をともなうものを主題にしているという点において、確かにコンセプチュアルではある。
当方的2018年展覧会ベスト10
年末なので、当方が今年見に行った483の展覧会の中から、個人的に良かった展覧会を10選んでみました。例によって順不同です。
・「唐代胡人俑 シルクロードを駆けた夢」展+「いまを表現する人間像」展@大阪市立東洋陶磁美術館

※「いまを表現する人間像」展出展作家:イケムラレイコ、マーク・クイン、オシップ・ザッキン、佐藤忠良、ニキ・ド・サンファル、棚田康司、シュテファン・バルケンホール、舟越桂、マリノ・マリーニ
中国陝西省で2001年に発掘された陵墓から出土した胡人(中央アジアやイランにいた諸民族)や馬などが象られた俑の、フィギュラティヴな造型やディテールのデフォルメ具合が非常に見応えがあったが、(大阪市立東洋陶磁美術館の近所にある)国立国際美術館の彫刻コレクションの出張展示といった趣の「いまを表現する人間像」展が同時に開催されていたことで、古代中国の文物を鑑賞するというところにとどまらないアクチュアリティにも届いていたのが個人的には非常にポイント高。現代、とりわけ二度の世界大戦を経た中で/後で作られた具象彫刻は、近代的な人間像を全面的に懐疑するところから始まっているのだが、そのような彫刻が必然的に帯びることになるフィギュラティヴなものと、近代的人間など全くいなかったであろう8世紀中国におけるフィギュラティヴなものとを同時開催という形で見せることで、近代的人間像とは何か/何だったのかについて考えさせるものとなっていた。

同時代人であり、いわゆる「阪神間モダニズム」の空気を存分に吸って育ったという共通点があるものの、かたや西洋画〜東京芸大教授、かたや抽象画〜具体美術協会の総帥というほとんど真逆な画業を歩んだためか、これまで並置されることがほとんどなかった小磯良平(1903〜88)と吉原治良(1905〜72)の作品を年代ごとに「並べて見せる」ことに特化した展覧会。展示室のどこにおいても視界に二人の作品が入るようにしつらえられていたわけで、その「並べて見せる」ことへのこだわりは半端なかったのだが、そうすることによってそんな二人が一瞬歩み寄る瞬間が意外とあったこと──それは、同じ本(林芙美子の小説)の装丁に小磯verと吉原verがあったという唯一の決定的な交点があったという事実によって、さらに強調されるだろう──が容易に見出されるように構成されており、作品が織りなす地平の中でランデブーを描くような軌跡を見せていたことがあった(けど、また互いに離れていった)ことが雄弁に語られていたわけで、モノグラフでは決して見えてこないものが可視化されていたと言えるだろう。
・「桂離宮のモダニズム 高知県立美術館所蔵石元泰博写真作品から」展@京都文化博物館(常設展フロア)

高知県立美術館が所蔵している、石元泰博(1921〜2012)が撮影した桂離宮の写真百数十点と、それをまとめた三種類の写真集(それぞれ1960年、1971年、1983年刊)という、小規模といえば小規模な企画だったが、巷間桂離宮の建築史的価値を決定づけ、ここから敷衍されるような形で日本建築の(西欧に先行すらした)モダニティを云々する言説に説得力を与えた仕事として現在もなお高く評価されている石元の写真や写真集を単に紹介するだけでなく、桂離宮とモダニズムの関係性を体現している(とされてきた)写真作品と、その関係性の歴史的な変遷の中で生じた揺らぎ──写真集の製作過程における丹下健三や亀倉雄策、ヴァルター・グロピウス、磯崎新らの影響が指摘されることになるだろう──の中で制作された写真集とを対置するという構成で一貫していたわけで、そこはなかなかクリティカルであった。桂離宮のみならず、日本建築(史)をめぐる言説全体にまで拡張して考えることを促す良展覧会。
・澤田華「見えないボールの跳ねる音」展@Gallery PARC

雑誌や写真集などのスチール写真の片隅に往々にして写っている、おそらく撮影者の意図と関係なく写りこんでいるであろう何かについて偏執的に検索したり調べ上げたりした過程を様々な形で提示するという作風で近年注目を集めている様子の澤田華(1990〜)女史の良質な側面がよく出ていた展覧会。ここではMr.ビーンでおなじみの俳優ローワン・アトキンソンのポートレイト写真に写りこんでいた何かについて調べ上げていたのだが、プリントアウトされた画像検索の結果やカラーチャートの束を追っていくことが、しかし結果につながらず「写っているものごと」と「写っていない外的現実」との関係──写真はそれを写すことができない──と、そのいびつなあり方/ありようへと鑑賞者を強制的に開いてしまうわけで、それは端的に上手いなぁと思うことしきり。
・伊吹拓「葆光」展@GALLERY wks.

関西を中心に抽象画を描き続けている伊吹拓(1976〜)氏の、GALLERY wks.では15年ぶりとなった個展。やはり壁一面に自身が描いたドローイングやペインティングを大量に切り貼りした《葆光》(画像参照)が圧巻。絵画空間内における遠近や前後が攪乱された/されつつある画面を作るところに伊吹氏の抽象画の特質があるのだが、ナイフによって自身の作品をメタ的なレベルにおいてカットアップ&リミックスされる形で再描することで、レイヤーの複数性という位相に安易に還元するのではなく壁とドローイングという一層のみにあえて局限していたわけで、そのストイックさは、同時代・同年代の画家の中でもかなり際立っている。伊吹氏は「(制作している過程において)絵に攻撃された」という非常に印象的な表現で制作裏話を語っていたが、このような感覚とともに作られたことで、《葆光》は自身の抽象画の、そしてそこにとどまらない日本の抽象絵画の別の可能性を垣間見せていたと言えるかもしれない。
・田村友一郎「叫び声/Hell Scream」展@京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA

詳細はこちら→
田村友一郎「叫び声/Hell Scream」展 – あたしか – Medium
ここ十数年ほどのトレンドとして、美術家が歴史的な史料/資料をリサーチした成果を用いて作品や展覧会を作るというムーヴメントが日本でも盛んになってきており、今年のそのような展覧会が各所で開催されていたのだが、その中でも「「美術家」がそのような行為を行なうこと」の意味が最も強く現われていたのがこの展覧会。自身の名前「田村」を用いて「田能村(直入)」や「(小野)篁」「田村(勤)」といった登場人物からなる資料や事物にまつわる歴史の中に自分自身も嵌入させ、そうして別の歴史を語ってしまう手腕の巧みさには唸ってしまうことしきり。リサーチ系の展覧会については、とりわけ予算や準備期間の事情から、本職の学芸員が本気出したら一蹴されてしまうだろうなぁという憾みもなしとはできないものが散見されるだけに、自身(の名前)の記号的操作を前面に押し出したことで、端的に今後の範となるだろう。
・「プレスアルト誌と戦後関西の広告」展@大阪府立江之子島文化芸術創造センター

1930年代から1970年代にかけて大阪で発行されていた「プレスアルト」という広告雑誌を中心にして戦後の関西企業の広告を見ていくという展覧会だったのだが、何よりもプレスアルトの存在感がインパクト大。実際のポスターやパッケージなどを記事とともに無理矢理綴じて本にして出すという形で出版されており、モノとしての存在感のレベルが違っていたわけで。しかもそんな破天荒な雑誌が40年近くにわたって発行され続けていたことに、この時期の(現在は失われた)大阪経済の深さを見ることもできるだろう。広告とは何よりもまず広告物であるという、おそらくこの雑誌を支えていたであろう認識は、マーシャル・マクルーハンが唱えた「メディアはメッセージである」という認識やそれを前提とする社会学とは異なった形で広告という存在へのアプローチを鑑賞者側に促していたと言えるだろう。
・「北辻良央の70年代」展+「WORK - Unterm Rad(車輪の下)」展@+Y GALLERY

地形図の模写や眼前の風景を記憶を頼りに描き出すといった同じ行為を何度も繰り返すというコンセプチュアルな作品で70年代前半にデビューした北辻良央(1948〜)氏は、80年代に入ると人物像やオブジェなどで物語を表現するような作品へと移行する。個人的にはその間に一体何があったのか全く窺い知れず、長年の謎だったもので、それが今回のこれらの展覧会でだいぶ氷解した次第。記憶したものごとを反復して描き出すという行為は最初から必然的にズレを孕んでおり、そのズレ=差異(もしくは「差延」((C)デリダ)と言った方が適当か)は身体を介して複数の位相、複数の記憶へと広がっていき、それが物語性を導入するきっかけとなる──以上のような理路を経て北辻氏の超展開はなされることになるのだが、そのプロセスをモノグラフィという形で制作の論理の内的な超展開として作品を通して見せていたわけで、普通に勉強になった。現在1980年代を回顧する展覧会が二つ同時に開催中(「起点としての80年代」展、「ニュー・ウェイブ 現代美術の80年代」展)だが、これらに関連して関西各所で開かれていた回顧展的性格を持った展覧会の中でも際立ったクオリティの高さを見せていたと言えるだろう。
・小松原智史「巣をつくる」展@the three konohana

大きな紙に模様ともクリーチャーとも見える謎のモティーフを延々描き続けるという作風で2013年に岡本太郎現代美術賞に入選するなど、以前から活躍していた小松原智史(1989〜)氏だが、そんな氏の新作はこれまでの二次元から、仮設された構造物を加えた三次元的な作品へと変わっていた。その意味で絵画・平面からインスタレーションへと展開していったことになるのだが、この展開が恣意的なものではなく、ある(歴史的・)論理的な強度をともなった展開であることが感得されたわけで、個人的には非常に驚くことしきり。かつて関西ニューウェーブの渦中に画家としてデビューした山部泰司(1958〜)氏は「絵画の枠を外すとインスタレーションになる」と発言していたが、小松原氏の今回の作品は、ともすると空間・立体の問題系と接続されることの多いインスタレーションについて別の位相がありえた/ありえることを雄弁に示していたし、80年代の絵画・インスタレーションの現在における可能性を作品を通じて垣間見せていたことは特筆されるべきだろう。「個体発生は系統発生を繰り返す」。
・松平莉奈「悪報をみる─『日本霊異記』を絵画化する─」展@KAHO GALLERY

京都における若手の日本画家の中でも近年最も精力的に活動している一人である松平莉奈(1989〜)女史。そんな彼女が9世紀ごろに書かれた仏教説話集『日本霊異記』からいくつかの話をピックアップして挿絵の要領で描いた作品が並んでいたこの展覧会は、古典を現代人の話として置き換えて描くメチエの巧みさが際立っていて、日本画としての良さを堪能できる良い機会となったのだが、そこにとどまらず、思想的な位相にまで踏み込んで描き出していたわけで、そこはなかなかポイント高。よく知られているように『日本霊異記』は日本初の仏教説話集だが、松平女史はこの本の特徴として現世での悪事の報いを現世で受ける筋立ての話が多いことに着目し、そういう話を多くチョイスして絵画化したという。来世や浄土、輪廻転生といった、仏教説話においてよくイメージされる要素が少ないことに着目していたわけで、そこに日本思想の通奏低音((C)丸山眞男)を見るという態度は、彼女がクリスチャンであることも含めて、オルタナティヴな日本画について考える上で、示唆に富んでいる。
中小路萌美「かたちのいのち」展

西天満にあるOギャラリーeyesで4月9〜14日の開催されていた中小路萌美「かたちのいのち」展。昨年(2017年)のシェル美術賞に入選するなど近年進境著しい中小路女史ですが、ここ数年毎年この時期にOギャラリーeyesで個展を行なっております。当方は一昨年から毎年彼女の個展に接しておりまして、今年も最終日になんとか拝見できた次第。
さておき、今回も大小十数点の新作絵画が出展されていました。中小路女史の絵画は、不定形な色面がランダムに配置された抽象画といった趣を見せていますが、最初に風景画を描き、その中の様々なモティーフを切り取って色面に還元した上でコラージュし、それをモティーフにして改めて絵画を描くというプロセスを経て制作されています。風景画から切り取られた諸要素が画面の中にフォルムに還元され、改めて緩やかに並存しつつ結合するという形で描かれているわけですね。昨年のシェル美術賞で入選した作品も、そのようにして描かれている。ですから、具象的なものごとから完全に解離した、あるいはそうあることが目指されている抽象画というわけではなく、コラージュ的に描かれた構成要素が以上のようなプロセスを経て改めて見出され使われていることで、どこか私たちの生きている生活世界との接点が残されているように見えるわけです。その意味で彼女の抽象画は、その歴史の中で蓄積されてきたであろうような、生活世界から解離され還元された形態や色彩の存在感やせめぎ合いをそのまま見せること──巷間、抽象画が意味不明なものとして受け取られてしまうのは、かような行為が広く共有されていないことに起因すると言えるでしょう──とはやや違った方向性を志向していると言えるでしょう。実際、中小路女史は以前の個展において「言葉には上手くできない。/見えているけど見えていない。触れそうなのに触れない」や「アクリル板で隔たれた向こう側」といったフレーズで、自身の抽象画の目指す方向性を表現していました。私はあくまでも世界-内的な身体的存在である、というところを出発点にして抽象画を作り出していくという試み。
ところで今回の「かたちのいのち」展においては、上述したようなプロセスの大枠は変わっていないものの、いくつかの作品において筆の痕跡がこれまでよりも強調されていたり、あるいは風景に由来しない要素が絵の中に外挿されたりしていました。かような変化が一過性のものなのか今後も続く本質的な変化なのかは現時点では判断できませんが、個人的にはこの展開は非常に興味深いものがありました。これについては、在廊していた中小路女史と歓談した際、自身の中にある心的な感覚(の変化)が露出してきたものと説明されていましたが、ここには単なる心境の変化に還元しきれない〈ペインタリーなもの〉にかかわる何かが露呈しているように、個人的には思うところ。
先ほども述べたように、中小路女史の作品は、私はあくまでも世界-内的な身体的存在であるというところを出発点にしているという一点において、シュルレアリスムと親和性が高い作風を取っていると考えられます。それは絵のみならず、絵のタイトルがひらがなをランダムに並べて作られた謎フレーズであるというところにも、如実に現われている。《にゆある》《らとり》といった出展作品のタイトルは、何やら自動筆記された結果出てきたものであるように見えてきます。言うまでもないが、自動筆記はシュルレアリスムの提唱者アンドレ・ブルトンにおいては基本中の基本となる行為であった。そういうところにも中小路女史の仕事とシュルレアリスムとの並行性を見出すことは困難ではないでしょう。しかしその一方で、今回の出展作における作風の変化は、彼女の作品とシュルレアリスムとの関係をさらに更新させるものとなっているのではないか。
かかる中小路女史の作風の変化は、自身の中にある心的な感覚(の変化)が露出してきたものとされているわけですが、それが表現の位相においては自分自身と下意識的な何か──よく言われる「無意識」よりも(同じUnbewusstseinの訳語として当初採用されていた)「下意識」の方が、中小路女史のかような新展開について考える上でより適当であるように思われます──との関係を、単純な意識-無意識という対にとどまらないものにさせている。表現という形を取ることで、これまでの作品の中において浮遊感をともないつつも画面を収めていた遠近法に別種の遠近法を与えられており、それによって絵の中でさらに複雑な心的構造を形成しているわけですね。このとき、表現は表現されるものの単純な反映ではなくなるだろう。というか(私たちが通俗的に理解していることとは逆に)表現において、表現の位相においてはじめて無意識・下意識が存在することになる。言い換えるなら無意識・下意識は世界-内的な身体においてというより、そこからの切断によって存在する。絵画における〈ペインタリーなもの〉とは、そのような切断のことにほかならない。
そういうダイナミズムが今回の「かたちのいのち」展の出展作に見られる作風の変化において、私たちの目にもハッキリと分かるように導入されていたわけで、個人的には大いに瞠目しきり。この展開は、端的に良い。画像はその展開が小品ながらギュッと詰まっていた作品《をるゆ》(当方蔵)。

笹山直規「SOMEBODY」展

中津にあるAIDA Galleryで3月30日〜4月15日の日程で開催されていた笹山直規「SOMEBODY」展は、ゼロ年代から画家として精力的に活動してきている笹山直規(1981〜)氏の、大阪では数年ぶりとなる個展でした。AIDA Galleryに加えて、隣室──現代美術家で、数年前に沖縄県に拠点を移した高須健市氏の自宅兼ギャラリースペース「ART SPACE ZERO-ONE」だった場所──も会場にしており、今回の個展に合わせて制作された新作から旧作に至るまで体系的に見ることができるものとなっており、笹山氏の画業の全貌とは言えないにしても、主要な部分をカバーする規模のものとなっていたと言えるでしょう。
さておき笹山氏は以前から、ネットで拾った死体写真をモティーフにした絵画を描き続けていることで知られています。当方は主に氏がキュレーションしたグループ展で何点かに接したことがありますが、個展は初めてでして。死体をモティーフにし、その死に様をかなり直截に描いているということもあって、展覧会のたびに激しい毀誉褒貶をネット界隈に巻き起こし炎上している様子の笹山氏ですが、実際に作品に接してみると、「死体をモティーフにしている」という言葉から喚起されるようなグロさや境界侵犯的なニュアンス、あるいはアングラカルチャー的なノリよりも、むしろ死体をモノとしてゴロンと提示する感じに描き出すことの方に力が注がれているように感じられる。そういう意味では「SOMEBODY」という展覧会タイトルは非常に示唆的であるし、きわめて相応しいものとなっています──笹山氏においては、「死体を描く」ことを直接的に希求すること以上に「「死体」という特殊例を通して人体を描く」という志向の方がはるかに際立っており、従ってそこでは死および死体は匿名化されることになり、個々の人間の個々の死は、少なくとも描かれた絵から類推する限り、氏の実践の外側にあるように見えるからです。
改めて言うまでもないことですが、人体を描くこと、ことに(神の似姿として)理想化された人体を描くことは、西洋絵画の中において厳然たる伝統として存在してきた/存在している。笹山氏は今回配布していたステイトメントにおいて自身の死体画がそういった西洋絵画史との対質において、その伝統に(逆立的にせよ)連なるものとして存在していることを強調していますが、それを読みつつ実際に出展された作品に接してみると、死体をグロ画像として描くこととは真逆の志向性に貫かれていることがわかります。それは、笹山氏の作品とその受け入れられ方をめぐる現状に対して一定の修正を求めることになるのではないでしょうか。これまでの笹山氏の作品をめぐる批評は量的にも決して多くなかったばかりか、氏の絵画についての議論が、このようなモティーフの絵画の社会における受け入れられ方/拒絶され方をめぐる議論に横滑りしてしまい、結果として死体というモティーフをめぐる倫理的な是非ばかりが前面化され、絵画としての出来やアクチュアリティについての議論が置き去りにされてしまうきらいがあったからです。言い換えるなら、死体を描くことをセンセーショナルなものとする「俗情との結託」が、笹山氏の絵画をめぐる本質的議論を抑圧してきたわけで。それは言うまでもなく健全な状況ではないのですが、かかる現状をほどくための言葉を、しかし自分自身で書く/書かざるを得ないところに、笹山氏をめぐる言説的な状況の悪さが存在する。
──少々横道にそれてしまいましたが、ここではかかる死体画が「歪んだ身体」「ねじ曲げられた身体」「溶かされた身体」といった、ことに20世紀以後の西洋絵画において言説的・修辞的な次元においてロマン化された身体像に対する強烈な介入としてあることにも注目しなければなりません。上述したように、笹山氏において死体画は、死因は何であれ死体を何かの説話論的な象徴としてアレゴリカルに提示すること以上に、その物体性がダイレクトに描き出されるものとしてあるのですが、しかし実際に作品に接してみると、基本的に水彩画であることも手伝ってか、全体として静謐な印象を見る側に与えるものとなっている。笹山氏は今回の個展に先立って、死体写真家としてその筋ではよく知られている釣崎清隆氏とともに──治安の悪さが日本でもしばしば話題になる──メキシコに赴いたそうですが、それがいかなる成果をあげたかについては部外者的には窺い知れないものの、死体に対する氏の視線の「質」をより深めるものとなったことは、今回出展されていた絵画からも十分に伝わったのでした。
伊東宣明「生きている/生きていない 2012-2017」展

いささか旧聞に属する話ですが、galerie 16で昨年12月12〜24日に開催されていた伊東宣明「生きている/生きていない 2012-2017」展は、関西を中心に活動している伊東宣明(1981〜)氏の、関西では数年ぶりとなる個展でした。伊東氏は、galerie 16では初個展から間もない2008年に一度個展を開催しておりまして、今回はそれ以来およそ10年ぶりとなるそうですが、この間、主に映像作品を中心に制作活動を続ける中で京都のみならず東京や名古屋でも個展を開催するようになったり、近年は京都造形芸術大学が運営するARTZONEのディレクターとしても同大学でアートマネジメントを学ぶ学生を率いて辣腕を振るうなど、活動の場を大きく広げてきている。その意味で今回の個展は、キャリアをしっかり重ねてきた上で満を持して凱旋してきたという趣があったと言えるでしょう。
さておき、展覧会タイトルからも分かるように、今回は伊東氏が2012年以来手がけている《生きている/生きていない》シリーズが出展されていました。 全裸の伊東氏が聴診器で自身の心音を聴きながら、そのリズムに合わせて生肉の塊を拳で叩いていくという行為とシチュエーションを記録した数分ほどの映像作品ですが、2012年の第一作以来、おおむね一年に一作のペースで作られており、今や伊東氏の代表作と言ってもあながち揚言ではない。第一作では白い背景で行なわれていたのが、竹藪の中や山水画のような光景が広がる海辺、洋間、病院の廊下、果ては(岡山市にあるS-HOUSE Museum( http://s-house-museum.com/ )が所蔵している)加藤泉氏の彫刻作品を背景にして行なわれておりまして、映像内での伊東氏の行為やそれが行なわれているシチュエーションの突飛さを見るべき作品となっています。今回は、ギャラリー内の壁面に二画面に分け、双方の画面に映写された各作品がシンコペーションを変えながらループしていく――そのため、同じ映像が同時に現われることはない――という形で構成されていました。このような見せ方で《生きている/生きていない》に接することは管見の限りでは今までなかっただけに最初チト戸惑いましたが、ずっと見ていると、かような構成を取ることで、映像に映し出されたヴィジュアル的なシュールさとはまた違った角度からこの作品を見直す必要があるなぁと思わされることしきり。
ことにそれは伊東氏の別の過去作と交差させることで、より明らかになるだろう。 これまで伊東氏は複数の画面を用いたり、映像内の要素がそのままで別のモノ・コトをも同時に指し示している(ように観客視点からは見えてしまう)事態を繰り込んだりした映像作品を手がけてきていることで知られています。上述したように伊東氏は10年ほど前にもgalerie 16で個展を開催していますが、その際に出展されていた《幻視者/演者と質問者》では“催眠術にかかった人”と“その人の演技をする人”をそれぞれ二画面で映し出してましたし、今はなきサントリーミュージアムで開催された「レゾナンス」展(2010)で展示されていた《死者/生者》では、うわ言を発している伊東氏の祖母の映像と彼女のマネをする伊東氏自身が、やはりそれぞれ二画面で映し出されていました。さらに数年前の《芸術家》では、駆け出しの女性アーティストに自作の(過去の大芸術家たちの名言をピックアップした)「芸術家十則」なるアフォリズム集をムリヤリ記憶させ、大声で早口で喋らせる(で、途中でトチったら最初からやり直させる)という、ブラック企業の社員研修にありがちな無意味な行為を延々とさせる様子を映し出していた――といった具合に、これらの作品においては、映像に映し出された事態の主体が(二画面の相互間で)決定不能状態に陥っている様子が執拗に主題化されているわけです。で、それは、《芸術家》において、「芸術とは/芸術家とは」という陳腐な問いに対して、「これを暗記して正しく暗唱できたら(誰であれ)芸術家である」というメタ的な位相を唐突に挟み込むことで問いが二重化されるという形で、形式論理的な操作という面においてひとつの極点を見せることになる。
《生きている/生きていない》に戻りますと、この中で伊東氏が執拗に行なっている肉塊を叩くという行為は、草創期のトーキー映画において心音をローテクに再現する方法として考案されたものだそうです。大昔の時代劇においてキャベツをざく切りするときに出る音がチャンバラシーンで人が斬られたときの効果音として使われてた――というのと同じアレですね。そのことを勘案してから改めて映像作品に接してみますと、一見すると謎の行為を単に延々と映し出しているだけのように見えるこの作品も、実際の心音とローテク効果音として作られた心音という形で二重化された様態が映されていることになり、先にあげた過去作と同じ問題意識を共有して制作されたものであることが見えてきます。しかもそういう仕掛けを内容に埋めこんだ作品を二画面で提示するという形で、今回の展覧会ではさらに徹底された形で開示されているわけですから、かつての《芸術家》と同程度には極致に達していたと言えるでしょう。
――いずれにしましても、伊東氏の作品に頻出する二重化というモーメントが、一見するとそう見えない作品にも貫かれていることがかような形で示されたのが、個人的には大きな収穫でした。
当方的2017年展覧会ベスト10
年末なので、当方が今年見に行った552の展覧会の中から、個人的に良かった展覧会を10個選んでみました。例によって順不同です。

・「泉茂 ハンサムな絵のつくりかた」展/「泉茂 PAINTINGS1971-93」展(1.27-3.26 和歌山県立近代美術館/2.25-3.26 Yoshimi Arts, the three konohana)
関西の美術館における常設展でその作品に接することが多い泉茂(1922〜95)だが、それゆえにか、一定のパースペクティヴのもとで集中して展観する機会はこれまで多くなかったわけで、美術館/ギャラリーという垣根を超えて緊密な連携のもとで行なわれた両展は関西においても貴重な機会となった。和歌山県立近美では通時的に、Yoshimi Artsとthe three konohanaでは1970年代から晩年に至るまでの絵画に焦点を当てて見せるという役割分担が行なわれていたのだが、そのことによって、泉の画業が作風の大胆な変更を繰り返していてもなお、「構造」の導入による画面の(モティーフの具象性や物語性からの)自立というモーメントにおいて一貫していたことが強い説得力を持って明らかにされていたわけで、個人的には非常に勉強になった。

・西山美なコ「wall works」展(10.24-11.12 Yoshimi Arts)
1990年代に少女趣味的あるいは少女マンガ的な意匠をあからさまに導入することによって女性性を外面的・形式的な位相に定位するような作品を多く制作したことで、前時代のいわゆる「超少女」と呼ばれた一群の女性作家たちに対する批評的な視線を内在化させた作品を多く作りだしてきた西山美なコ女史だが、近年は展示空間の壁面に直接描く作品を多く手がけているそうで。その現時点における最新版がこの展覧会だったのだが、ギャラリーの壁面にピンク色の二つの円がボヤッと浮かび上がっているという、それだけといえばそれだけ(ただし、労力は相当かかっている)の作品でありながら、ずっと見ていると視覚的にハレーションを起こすことしきり。かような形でオプ・アートを導入することで、身体に対する新たなアプローチを見せたことの意味は、身体を本質化することで90年代以降急速に反動化していったフェミニズム――西山女史の作品は、ことの最初からフェミニズム批評であり、その意味でポストフェミニズムなのである――と美術との関係を再考する上でも重要であろう。

・「福岡道雄 つくらない彫刻家」展(10.28-12.24 国立国際美術館)
大阪の現代美術界隈におけるビッグネームの一人として知られる福岡道雄(1936〜)氏の大規模な回顧展。初期作品から「つくらない彫刻家」宣言をした後の近作まで、彫刻のみならず平面なども大量に展示されていたのだが、ほとんど別人のごとき作風の変化を超えて一貫しているのは「つくる」ことを自明視することへの違和感の表明であり――既に最初期の頃に「なに一つ作らないで作家でいられること、これが僕の理想である」と表明しているのだから、相当筋金入りである――、そこから始まる迷走と中断、私的なものとの接近と乖離の軌跡をこそ見るべき展覧会であると言えるかもしれない。反芸術はなやかなりし頃に、その近傍から出てきつつ、ときに具象彫刻を作ったり、今なお豊かな謎をたたえる〈風景彫刻〉を作ったり、「何もすることがない」と大画面に細かく繰り返し書いて埋め尽くしたり……と、同年代の作家と比べてもその振れ方の凄まじさに眩暈を覚えることもないではないのだが、「反」の意味自体を問い直すこととあわせて最も「反芸術」していたのが福岡氏だったのかもしれない――そのようなことを考えさせられた。

・「抽象の力 岡﨑乾二郎の認識――現実(Concrete)展開する、抽象芸術の系譜」展(4.22-6.11 豊田市美術館)
※主催:豊田市美術館
※協力:武蔵野美術大学美術館・図書館
※企画監修:岡﨑乾二郎
※出展作家:フリードリヒ・フレーベル、マリア・モンテッソーリ、ルドルフ・シュタイナー、高松次郎、田中敦子、イミ・クネーベル、ブリンキー・パレルモ、ヨーゼフ・ボイス、ウルリヒ・リュックリーム、恩地孝四郎、熊谷守一、マルセル・デュシャン&ジャック・ヴィヨン、ジョルジュ・ブラック、エドワード・ワズワース、ドナルド・ジャッド、コンスタンティン・ブランクーシ、ペーター・ベーレンス/AEG社、ヘリット・トーマス・リートフェルト、斎藤義重、長谷川三郎、村山知義、吉原治良、ゾフィー・トイベル=アルプ、ハンス・アルプ、ジョン・ケージ、テオ・ファン・ドゥースドルフ、ピエト・モンドリアン、バート・ファン・デル・レック、瑛九、岸田劉生、坂田一男、中村彝、サルバドール・ダリ、ジョルジョ・モランディ、ル・コルビュジエ、フェルナン・レジェ、ジャン・デュビュッフェ、ルーチョ・フォンタナ、ダヴィド・ブルリューク、フランシス・ベーコン
※他、熊谷守一日記帳、ヒルマ・アフ・クリント作品のコピー、『MAVO』1-7号、『FRONT』1-10号、岸田日出刀ほか編『現代建築大観』挿画、デ・ステイル誌、『アブストラクシオン・クレアシオン』1-5号、『291』5・6号、キャサリン・ドライヤー『ブルリューク』などの各種資料
《キュビスム以降の芸術の展開の核心にあったのは唯物論である》《物質、事物は知覚をとびこえて直接、精神に働きかける。その具体性、直接性こそ抽象芸術が追究してきたものだった。アヴァンギャルド芸術の最大の武器は抽象芸術の持つ、この具体的な力であった》というステイトメントのもと、1920〜30年代をピークとして《(戦後において歪曲され忘却されていった)抽象芸術が本来、持っていたアヴァンギャルドとしての可能性を検証し直す》ことが目論まれていたのだが、岡﨑乾二郎氏による以上のような認識が、出展されていた作品が改めて並べ直されることによって眼前において雄弁に語られていたことに、個人的には驚くばかり。テキスト( http://abstract-art-as-impact.org/ )が話題になっていた様子だが、実際には「見ること」をめぐる仕掛けが随所に仕掛けられていたことにこそ、この展覧会の眼目があったと言えるかもしれない。ことに「「抽象的に」世界を認識すること」の原風景として、フレーベルやモンテッソーリたちによる知育玩具が並べられた一直線上の向こう側に田中敦子の絵画作品を望むという動線の引き方は、岡﨑氏の認識を一見即解させるものとして、実に秀逸だったわけで。ここで超展開されていることが歴史的・思想的に見てどれほどの妥当性を持っているかについてはプロたちによる検証を待ちたいが、岡﨑氏によって周到にプログラムされたzipファイルが超速でダウンロードされインストールされていくような感覚は、まさに展覧会を実地において見ることの醍醐味にあふれていたと言えるだろう。

・「アペルト06 武田雄介」展(1.27-5.6 金沢21世紀美術館(長期インスタレーションルーム))
これまでインスタレーション作品を多く作り続けてきた武田氏だが、氏の地元での金沢での個展となった今回は、〈イメージの奥行き/イメージの湿度〉というテーマ(?)のもと、様々なオブジェや映像、写真etcがざっくばらんに並べられた空間を現出させていた( https://tmblr.co/Zq0wpx2LO3SeK )。「イメージ」に対し、その質的な様相に焦点が当てられていたわけであるが、武田氏の場合、そこにとどまらず、イメージを介した諸事物の平等という方向性がこの展覧会においてハッキリと打ち出されていたわけで、それは今日において非常に慧眼であると言えるだろう。武田氏が現出させた諸事物の平等は、イメージが質的存在であることを介することで、事物を認知する主体の想像力なしに実現されることになる――氏のインスタレーションにおいて映像が特権的な位置を占めていることは、想像力による因果関係(の補完)と別種の論理が伏在している(「自由間接話法」)ことを鑑みるに、示唆的であろう。それをインスタレーションという場の実践において継続的に行なっているところに武田氏の重要性があるし、それがこの展覧会においてこれまでとは違う高レベルでなされていたことに、私たちはもっと驚くべきなのかもしれない。

・「「1968年」無数の問いの噴出の時代」展(10.11-12.10 国立歴史民俗博物館)
フランスで起こった五月革命と呼応するように日本においてその前後に同時多発的に展開された諸運動に焦点を当てた展覧会。第一部ではベ平連や成田闘争、水俣病に代表される公害問題などといった形で具現化された市民運動が、第二部では大学紛争/全共闘運動がフィーチャーされていたのだが、膨大な資料とエピソードによって語られる出来事がいちいち興味深いわけで(とりわけ「長野県には「一人ベ平連」という運動があった」とか「水俣でばら撒かれた怪文書の実物」とか、普通に瞠目しきり)、それらを「無数の問いの噴出の時代」という形でパッケージングしたところに、主催者側の慧眼が光る――それは必然的に「無数の問い」を「唯一の回答」に回収する戦後民主主義への批判を(主張が表面的には一致していたにしても)潜在的に含みこんでいるからである。近年の動向として、日本における市民意識の頂点として1960年の安保闘争を置くか1968年前後の諸動向を置くかで大きく二分されてきているのだが、後者のアクチュアリティを現在において改めて見せたところに、この展覧会の特筆大書すべき美質が存在する。

・柳瀬安里「光のない。」展(3.7-12 KUNST ARZT)
今年も近現代史や社会的な諸問題を直接的に主題とした作品ないしプロジェクト――それらは往々にして「Socially Engaged Art」(SEA)と呼ばれている――を目にする機会がそれなりにあり、特に「戦後日本」という時空間を俎上に乗せることで近現代史を主題とした展覧会にエッジの効いたものがいくつかあったのは個人的に大きな収穫だったのだが(笹川治子「リコレクション―ベニヤの魚」展(8.25〜9.17 Yoshimi Arts)、井上裕加里「堆積する空気」展(8.1〜13 Gallery PARC)など)、その中でもダントツにヤバかったのがこれ。米軍のヘリパッド建設問題で反対派と機動隊が真っ向から衝突している沖縄県東村の高江地区に赴き、建設現場の近辺をエルフリーデ・イェリネクの戯曲『光のない。』を朗読しながらめぐるという映像作品なのだが、同作において主題化されている(と考えられる)「私(たち)とは誰か」、あるいは「「私(たち)/彼(ら)」を分かつものは何か」という問いを、「私(たち)/彼(ら)」をめぐる争いが最も激烈な形で展開されている高江地区において再演するというフレームワークは、畢竟「私(たち)/彼(ら)」という線引きを固定的なものとさせてきた戦後日本/戦後民主主義に対する見直しを見る側に迫ることになるし、『光のない。』自体がもともと東日本大震災に触発されて、「デモクラシーの黄昏」というお題へのレスポンスとして書かれたという事実を外挿することで、沖縄における事態が端的に戦後民主主義の黄昏であることをも含むことになるだろう。それは「68年革命」とその日本における徴候としての「戦後民主主義批判」において既に告知され、露呈していたのではなかったか。SEA(や、それを持ち上げる社会学者)に欠けているのは、問題をそれとして取り上げるときのフレームワークに対する、かような批判なのである。
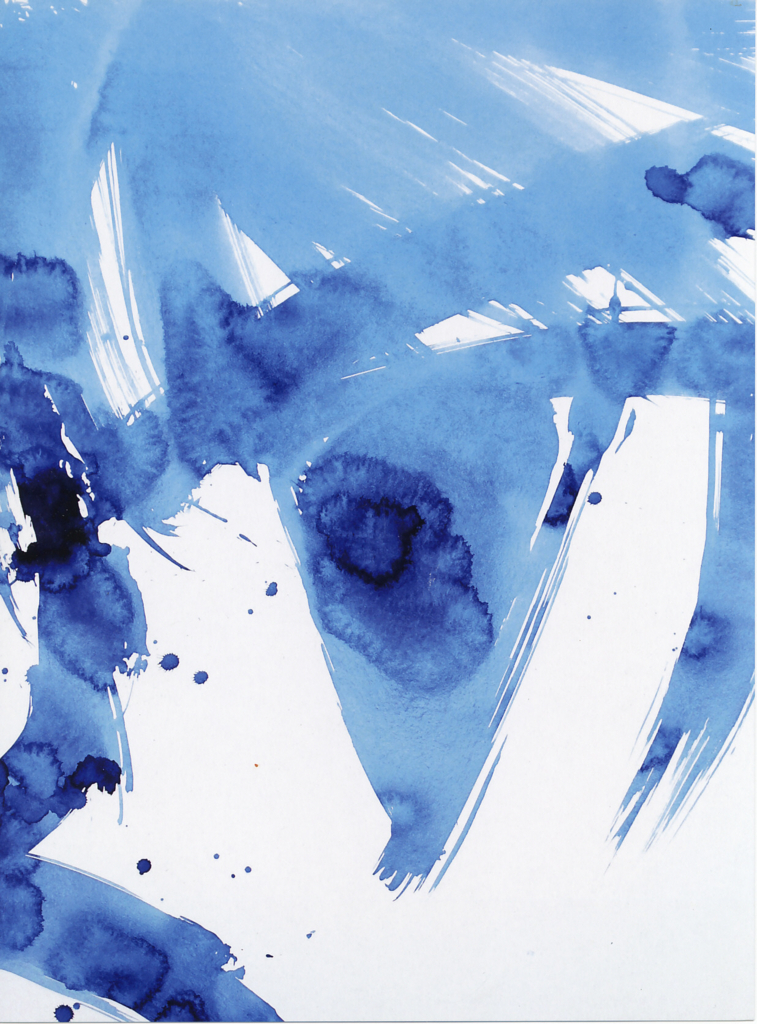
・清方「オーシャン」展(5.19-6.4 波さがしてっから)
清方(1990〜)氏の数年ぶりの個展となったこの展覧会の、京都というローカルな場におけるトランスローカルな史的過程という観点から見た位置づけについては会期中に書いたことがあるので( https://mastodon.xyz/@wakarimi075/3625002 )、詳しくはそちらを参照されたいが、そういった位相とも交差しつつ描かれていったのが「夏」や「海」を彷彿とさせる絵画であったことの意味もまた大きなものがあったのではないだろうか。ローカル/トランスローカルな位相におけるプロセスを経ることで、氏の描く「夏」や「海」が、かつて松井みどり女史がキューレーターとなって開催された「夏への扉:マイクロポップの時代」展(2007 水戸芸術館)への正当的な応答として機能していること、その意味で新しいSummer of Loveとなっていることが、今後の絵画において清方氏や、協力者としてクレジットされているKim Okko氏を正当に再評価する上で(この展覧会は、その序章である)真っ先に考察されるべきことなのかもしれない。
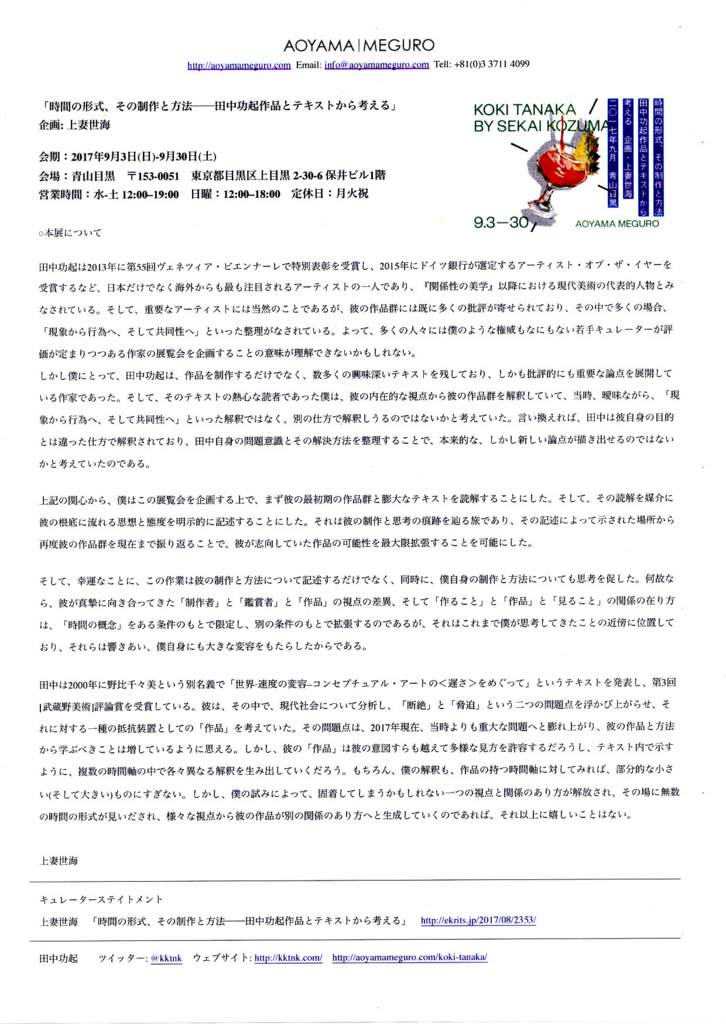
・「時間の形式、その制作と方法――田中功起作品とテキストから考える」展(9.3-30 青山|目黒)
田中功起氏の作品に対する長大な論( http://ekrits.jp/2017/08/2353/ )を提示し、それを発表/検証する場として展覧会という方法を用いるという上妻世海(1989〜)氏の企画力に、素直にすごいなぁと思ってしまうことしきりだった展覧会。大阪ではこういう企画はまぁ成立しない← それはともかくとして、田中氏が2000年に野比千々美名義で書いた論文「世界―速度の変容 ――コンセプチュアル・アートの「遅さ」をめぐって――」を出発点に、氏の名声を定着させた映像作品(同じ行為を複数の人間にさせる、というような)以前の、同じ状況が無限に繰り返されたり引き伸ばされたりしているような映像作品を多く選択し、それらを近年の(ポスト)関係性の美学の作家の一人としての田中氏に接続させるところに、上妻氏の賭金が存在していたのだが、そのような形で批評を展覧会に落とし込むのは、個人的には非常に新鮮な鑑賞体験だった。田中氏の制作活動を《バラバラになった僕たちを繋ぐ装置として、制作を考えていたのだ》という形で再提示(リバースエンジニアリング)するのは、今日において非常に重要な論点であろう。

・「不純物と免疫」展(10.14-11.26 トーキョーアーツアンドスペース本郷)
※出展作家:大和田俊、佐々木健、谷中佑輔、仲本拡史、百頭たけし、迎英里子
※キュレーター:長谷川新
※協賛:アイ・オー・データ機器、ERIKA MATSUSHIMA、gigei10
※協力:青山|目黒、スタジオ常世、This and That、tochka|特火点、PARADISE AIR
「批評」を提示/検証する場として展覧会という方法を用いつつ、こちらはもっと作品寄りというか、作品に語らせることに主眼を置いていた展覧会。ロベルト・エスポジトやジョルジュ・カンギレムの議論から着想されたと思しき自己免疫性の議論から出発しつつ、一定の度合いを越えると自己破壊を始めてしまう免疫システムからの連想で政治思想や社会思想を再考するという近年の動向に目配せしながら「不純物」としての作家と作品を提示するというフレームワーク――長谷川氏のテクスト「不純物と免疫」における《自分たち自身がまず「不純物」であり、また別の不純物たちとの折衝によってその都度規定されている存在として引き受ける地点が存在している》という一節は、それを端的に言い表している――は、今日における自己免疫性の全面化という状況に対する介入として、最低限踏まえていなければならないことであろう。なおこの展覧会は来年沖縄に巡回するという。自己免疫性の議論が最も試されている場所とも言える沖縄においてこの展覧会がどのように見られるか、興味深い。
森村誠「OTW / THC」展

この8月から10月にかけて大阪市内の二つのギャラリーで立て続けに開催された「THC」展(8.29〜9.9、於Calo Bookshop and Cafe)と「OTW」展(9.16〜10.22、於the three konohana)は、森村誠(1976〜)氏の未発表の旧作と新作を続けて見せることによって、氏の作品が潜在的に持っている別種の射程に見る側の注意を向けさせるものとなっており、その意味で非常に面白く、またアクチュアルでもあったと言えるでしょう。どちらも地図上の文字を一定の規則に従って切り取ったり修正液で消したりするという、近年の森村氏の作品の主軸をなしている作風が横溢していましたが、どちらもかような微細な行為の集積がそのまま別のアクチュアルな位相に接続されていく、その巧みさがきわめて印象的でした。
先に開催された「THC」展では、ニューヨークの地図や地下鉄路線図から「T」「H」「C」以外を修正液で塗りつぶした作品を中心に、数年前に制作されるも諸般の事情でこれまで展示されたことのない作品が出展されていました。「THC」とは大麻に含まれているヤバい成分の略称だそうで、この三文字に焦点を合わせることによって都市とドラッグないしドラッグカルチャーとの関係性が俎上に乗せられていると、さしあたっては言えるでしょう。で、それは、東京都の地図を用いた作品では「大」「麻」の二文字がくり抜かれていたり、以上のように加工された地図がドラッグカルチャー界の大物として知られるアメリカの詩人ウィリアム・バロウズ(1914〜97)の著作と並べられたり、さらにはくり抜かれた文字で作られた紙巻タバコ(っぽい何か)が並置されたり――当方が接した日には「モリムラナイト」ということで、タバコの葉をほぐして乾燥させて刻んだアジサイの葉っぱ(会場近辺の靱公園から採集してきたという)と混ぜて水増しし、紙巻タバコを改めて作るというパフォーマンスが行なわれてました――していることで、さらに強調されていた。かような具合に大麻を(あくまでも記号として、葉っぱそのものを使わない形ではあるにしても)前面に押し出しているわけですから、見ようによってはヤバいものがある。

一方、「OTW」展の出展作は、様々なギャラリーが展覧会の告知用に作るDMやフライヤーに付された地図を切り抜き、何枚も継ぎ合わせて一枚の平面にするというものでした――とひとことで書くと「THC」展とは対照的な単純な作品のように聞こえてしまうかもしれませんが、実際には文字情報を消去したり刺繍糸によって縫い合わされる形で継がれていたわけで(実際、いくつかの出展作は刺繍作品の制作途中のような形で展示されていた(画像参照))、こちらも「THC」展の出展作同様に微細な行為の集積によって作品が成立していた。個人的には展覧会に行った先で、あるいは行きつけのギャラリーから自宅に送られてきてこれらのDMやフライヤーに接する機会が多いので、作品を見てあぁこれは◯◯ギャラリーのから切り取られたものですねと、ギャラリスト氏と談笑したり。ちなみに展覧会タイトルの「OTW」とは「on tne way」の略とのことで、地図を使用した作品にふさわしいものとなっております。
消されたりくり抜かれたりした文字やそうされなかった文字を走査することで、“見慣れた地図”=“地図に表わされた実際の土地”に全く別の意味論的な相貌を与えてしまい、それによって「地図」と「土地」と「人間」との三項関係をハッキングしてしまう――地図を俎上に乗せた作品において森村氏が試みているのはそのような行為であると、さしあたっては言えるでしょう。しかし今回「THC」「OTW」と連続して個展を行なわれたことで見えてきたのは、かようなハッキング行為にドラッグ(カルチャー)という要素が加わることによって一回性ではなく大きなプロジェクトの一環であるという性格が付与され、それによってコンセプチュアルな一貫性が明確に与えられたということであると言わなければなりません。それはあからさまにドラッグ(カルチャー)を参照項としている「THC」展はもちろん、一見すると全く関係ないように見える「OTW」展にも見出されるのではないだろうか。
上述したように、「OTW」展ではギャラリーが出す各種フライヤーに付された行先案内図を切って貼った作品が多く出展されていましたが、それらは集積されて大きな地図を形作るというより、相互間の断絶や飛躍(まさにカットアップである)が強調され、全体としては地図としての用をなさないものとなっている。それは地図というより「地図」と「土地」と「人間」との三項関係が相互に切り離された後における心的地理を端的に示しているわけです。森村氏のハッキング行為は、「地図」が覆い隠してきた心的地理における断絶――これは街歩きを趣味にしている者なら多かれ少なかれ感じることでしょう――を改めて浮かび上がらせるものとなっている。特にギャラリーの地図は、デザイン性を重視するあまり地図としての用をなさなかったり(個人的な経験では、これは東京のギャラリーに多いような気がする)、近年では端的にスマホでグーグルマップとにらめっこしながら場所を確認するというスタイルに取って代わられていることもあって、三項関係やそれらのハッキング行為について格好のサンプルとなっているわけです。
こういった「地図」と「土地」と「人間」との三項関係と心的地理におけるその変質を、ヴァルター・ベンヤミンが「遊歩者」という形象――言うまでもなくベンヤミンにおいてそれは19世紀以降のブルジョワを担い手とする「大衆消費社会」がもたらした「夢」や「知覚様式」と結びつけられることになる(ただしブルジョワ=遊歩者と一概に言えないところにベンヤミン独特のややこしさがあるわけで…)――をその担い手として措定したように、私たちもドラッグ(カルチャー)に使嗾されたところから分析する必要があると言えるでしょう。